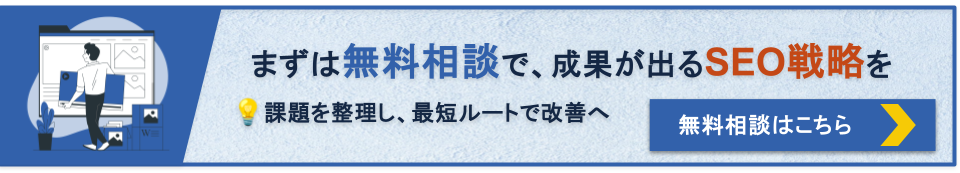ページロケーションとページパスの違いを徹底解説:初心者にも分かるウェブ解析の基本

はじめに:ページロケーションやページパスがよく分からない…
「ページロケーション」「ページパス」という言葉を耳にしても、その違いが何なのか、どう使い分ければ良いのか分からないという方は多いのではないでしょうか。特に、ウェブ解析やSEOの分野ではこうした用語が頻繁に登場するため、混乱しがちです。
実際に「このページロケーションって何?」「そもそもURLとどう違うの?」といった疑問を抱えたままでは、アクセス解析ツールを使いこなすことも難しくなります。この記事では、初心者の方でも理解できるようにページロケーションとページパスの基本を解説し、その違いや使い分け方を詳しく見ていきます。
この記事を読むメリット
- ページロケーションとページパスの意味と違いをしっかり理解できる
- ウェブサイト解析を正確に行うための基礎知識が身につく
- 具体例を交えた説明で、日常の運用に役立てやすい
ここから読み進めていただければ、ウェブサイトの構造をより深く理解し、ページの分析・改善にも役立てられるようになるはずです。
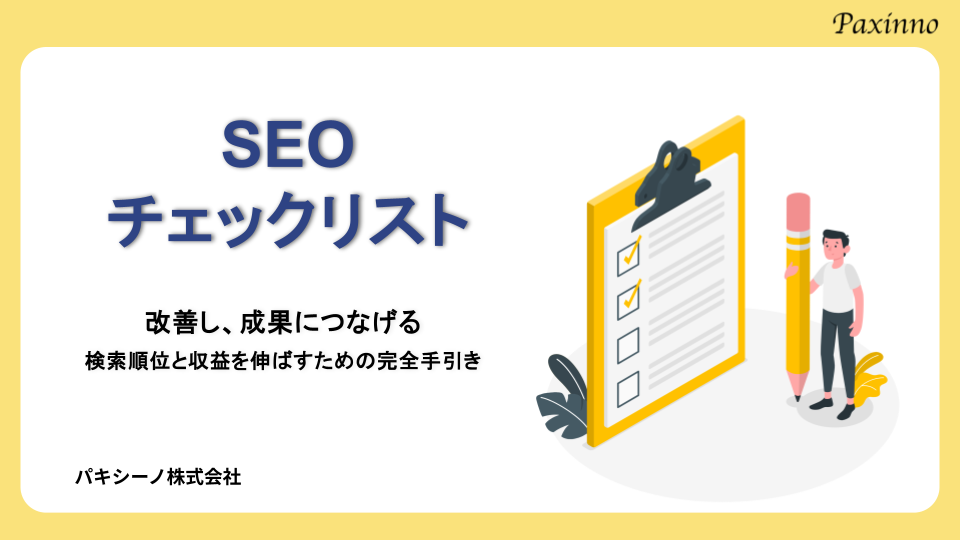
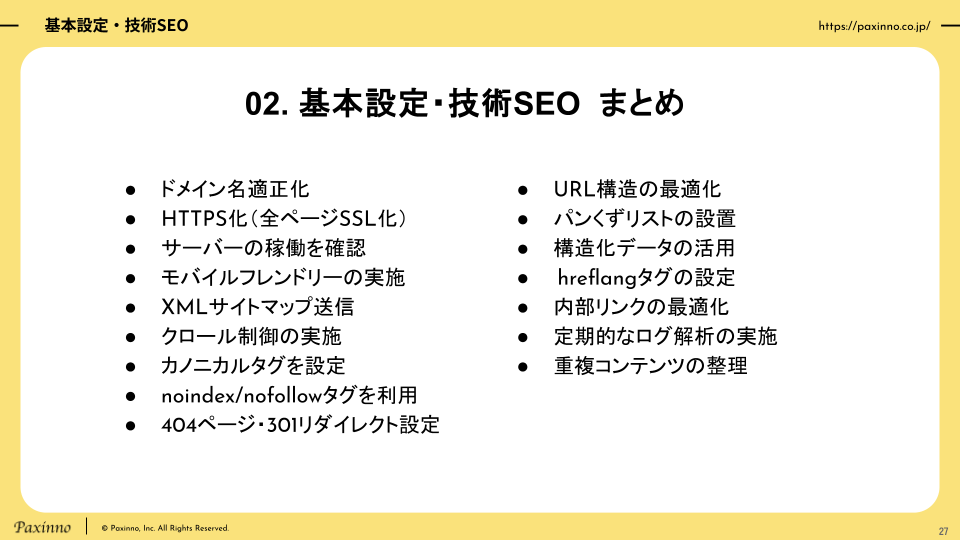
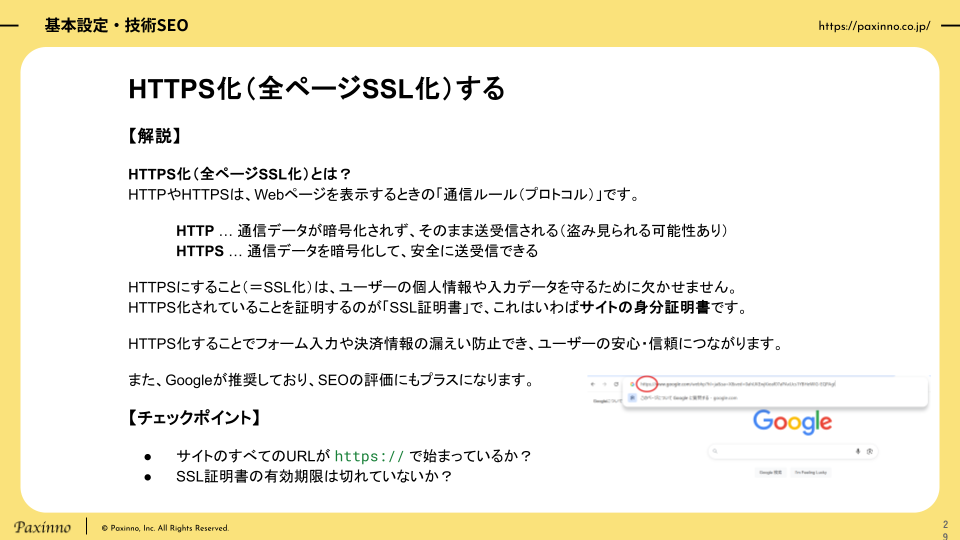
1. ページロケーションとページパスとは何か?
1-1. ページロケーションとは
ページロケーションは、一般的に「URL(Uniform Resource Locator)」とも呼ばれ、ウェブページが置かれている場所を示す情報です。たとえば、
https://example.com/blog/2025/02/02/sample-page
のような、完全なURL全体を指すイメージです。
アクセス解析ツール、特にGoogle Analyticsなどでは、ページロケーションが「プロトコル(httpsなど)」「ドメイン(example.comなど)」「パス(/blog/2025/...)」「クエリパラメータ(?id=xxx など)」を含んだ、いわゆるページの完全なアドレスとして扱われることが多くあります。
ウェブ解析の世界では、以下のようなタイミングでページロケーションという用語が登場します。
- Google Analyticsやその他解析ツールで、実際にユーザーがアクセスしたページの情報を取るとき
- クローラーの巡回や、検索結果からリンクされる際のURL管理
- SNSでシェアするときのリンクや、ユーザーがブックマークするときのアドレス
ページロケーションが重要な理由
- 一意にページを特定できる
- ページが属するプロトコルやドメインを区別できる
- パラメータ付きURLにも対応しやすい
もし解析画面でページロケーションを把握しておけば、ユーザーがどのドメインのどのプロトコル経由でアクセスしたか、またパラメータを使って特定キャンペーンからの訪問なのかを見分けることができます。
1-2. ページパスとは
ページパスは、上記URLのうち、ドメイン部分を取り除いた「ファイルパス」「仮想パス」にあたる部分を指します。先ほどの例URLで言うと、
https://example.com/blog/2025/02/02/sample-page
の「/blog/2025/02/02/sample-page」部分がページパスとなります。
アクセス解析ツールでは、特にGoogle Analytics(ユニバーサル アナリティクス)で「pagePath」というパラメータ名で扱われていたり、GA4でもデータ探索やレポート作成の際に「ページパス」「ページパスとクエリ」という名称が用いられたりします。
ページパスが重要な理由
- ドメインの異なるサイトや複数サブドメイン間の比較がしやすい
- URL構造の階層ごとにコンテンツを分類できる
- 表示URLが長い場合でも、ドメイン部分を除いて集約しやすい
大規模サイトや複数サイトを運営している場合、全てのページロケーションをそのまま扱うと非常に煩雑になります。ページパスを中心に分析することで、共通のフォルダ(ディレクトリ)ごとにページをセグメント分けし、コンテンツのパフォーマンスを比較検討しやすくなります。
SEO対策にお悩みの方へ
プロによる無料相談実施中!
プロによる1対1のヒアリングで、SEOのモヤモヤをスッキリ整理
2. ページロケーションとページパスの違いを比較
ここでは「ページロケーション」と「ページパス」の違いを、もう少し具体的に整理します。
| 項目 | ページロケーション | ページパス |
|---|---|---|
| 定義 | URL全体(プロトコル、ドメイン、パス、パラメータなどを含む) | ドメインを除いたパス部分(/ から始まる階層構造) |
| 活用シーン | ドメインやサブドメインなども含めてページを区別したい場合 | ページ階層の構造を比較・分析したい場合 |
| 解析ツールでの名称 | pageLocation (GA4) / Page URL (UA) | pagePath (GA4, UA) |
| メリット | プロトコル・ドメイン情報の把握、パラメータ付きURLの詳細分析 | サイト全体の階層別トラフィック把握、同一ドメイン内での比較がしやすい |
| 注意点 | 同じページパスでもドメインが違えば別URLとして集計される | ドメインをまたぐ分析には向かないため、別途ドメインやプロトコルを考慮する必要がある |
3. よくある混同例と初心者向けの注意点
3-1. 同じページパスでもドメインが違う場合
たとえば、企業が複数の国や地域向けにサイトを運営しているケースを考えてみます。
https://example.com/newshttps://jp.example.com/newshttps://us.example.com/news
これらのページは、ページパスとしてはすべて「/news」ですが、ページロケーションはそれぞれ別のURLになります。
https://example.com/newshttps://jp.example.com/newshttps://us.example.com/news
ドメインやサブドメインを含むことで、同じパスでも違うサイトだと区別できます。このため、トラフィックを合算すべきか、それとも国別に集計してそれぞれ比較するべきか、といった分析方針をあらかじめ明確にしておく必要があります。
3-2. パラメータ付きURLの扱い
ECサイトや検索機能のあるサイトなどでは、クエリパラメータが付いたURLが大量に生成される場合があります。
例:
https://example.com/items?category=shoes&color=red
この場合、ページロケーションとしては上記URLすべてが固有のアドレスになります。しかし、ページパスだけを見ると、
/items
となり、クエリパラメータ(?category=shoes&color=red)はページパスに含まれません。
「同じ商品ページだけど色が違う」「パラメータが異なる」など、場合によっては解析上で合算するのか、分離して集計するのか方針を決める必要があります。Google Analyticsやその他ツールでは、フィルタやレポート設定でパラメータを除外するかどうかをカスタマイズできるので、ページロケーションとページパスをどう管理するか考えておきましょう。
4. ウェブ解析での具体的な活用方法
4-1. GA4(Google Analytics 4)の事例
Google Analytics 4では、ページロケーションやページパスがイベントパラメータとして扱われています。以下は公式の情報から引用した一例です。
- page_location:完全なURL
- page_path + query_string:ドメインを除いたパス部分とクエリパラメータ
- page_title:ページのタイトル
大規模サイトでは、商品ページごとにパラメータが付与されるケースが多いため、page_locationを用いて詳細なキャンペーン効果や商品群の分析が可能になります。一方で、page_pathを使うことで、どのカテゴリ階層が人気を集めているのかをひと目で把握できます。
4-2. サイト運用におけるベストプラクティス
ページロケーションを使用する場合のヒント
- 異なるドメイン、サブドメインで同一ページパスを持つページの分析を分けたいときに便利
- パラメータ付きURLを細かく追跡してキャンペーンごとの流入を計測したい場合
ページパスを使用する場合のヒント
- 同一ドメイン内のコンテンツをディレクトリ単位でグループ化したいときに最適
- 階層構造(
/blog/、/product/、/support/など)ごとのトラフィック比較を容易にする - パラメータが多いサイトでは、クエリを除外しページをまとめて集計すると見やすい
5. ページロケーションとページパスを使い分けるメリット
初心者の方がいきなりアクセス解析ツールを開いたとき、似たような響きの用語が多数あって混乱するのは自然なことです。ただ、ページロケーションとページパスの違いを知り、使い分けることで、サイトの状況を多面的に見ることができます。
- ドメインやプロトコル単位の差異を分析したい
例:自社サイトが複数の国で運営されている場合、国別サイトの流入を把握できる。 - コンテンツの階層(カテゴリ)ごとの集客状況を知りたい
例:/blog/というフォルダ内の記事だけのPV数合計を調べて、どのテーマが人気かを分析。 - パラメータでタグ付けしたキャンペーンを評価したい
例:メールマガジン用のURLパラメータを使って、クリック率や購入率を細かく測定する。
いずれも、ページロケーションとページパスを適切に理解・設定していないと実現が難しいケースです。
6. 具体例でイメージをつかもう
6-1. 企業サイトの事例
大手企業が運営するサイトで、以下のような構造になっているとします。
https://www.example.co.jp/products/aaahttps://www.example.co.jp/products/bbbhttps://www.example.co.jp/blog/2025-02-02-releasehttps://www.example.co.jp/blog/seo-tips
ページロケーション:
- それぞれ完全なURL
(例:https://www.example.co.jp/products/aaaなど)
ページパス:
/products/aaa/products/bbb/blog/2025-02-02-release/blog/seo-tips
この場合、サイト内の「/products/」下にあるページだけを抽出して見たいときはページパスで絞り込みが可能です。同時に、もしパラメータをつけてキャンペーンを検証しているならば、ページロケーションを使うほうが詳細な結果を得られます。
6-2. アフィリエイトサイトの事例
アフィリエイトサイトでは、URLパラメータを付けてリンク先を計測することがよくあります。
https://affiliate.example.com/blog/recommend?ref=summer2025
ページパスだけでは「/blog/recommend」となってしまい、どのキャンペーン(ref=summer2025)が成果につながったか分かりづらいです。そこでページロケーションを見れば、パラメータ込みのURL単位で計測でき、どのキャンペーンがどのくらいの成果を出しているかを把握できます。
7. 注意点:解析の整合性を保つために
ページロケーションとページパスは、互いに補完し合う要素です。どちらか一方だけを見れば良いというよりは、目的に応じて使い分けるのがベストプラクティスです。
1) 余計なクエリパラメータの管理
ECサイトや大規模ブログでは、多数のクエリパラメータが生成されることがあります。Google Analyticsなどのツールでレポートが大量の類似URLに分割されてしまうと、分析しにくくなるのが難点です。そこで、特定のパラメータを集計から除外する設定をしたり、ページパスベースの集計でまとめたりと工夫しましょう。
2) サブドメインを跨ぐトラッキング
1つのブランドで複数のサブドメインを運用している場合、ページパスが同じでも別サイトとして扱われるため、データが分断されてしまいます。サブドメイン間トラッキング(クロスドメイン トラッキング)を設定し、ドメイン情報を引き継いだうえで解析できるようにしておきます。
3) 正しい命名規則・URL構造の設計
ウェブサイトのリニューアルや新規立ち上げの際に、URLの設計が曖昧だと、のちに解析が複雑になる場合があります。可能な限り、階層構造が一貫するわかりやすいページパスを採用し、クエリパラメータの数は必要最小限に留めると、運用がスムーズになります。
結論:正しい使い分けで分析精度アップ
ページロケーションとページパスの違いを理解し、目的に合わせて使い分けることが、ウェブ解析やSEOの土台になります。
- ドメインやプロトコル、パラメータを含めて詳細な情報を追いたいならばページロケーション
- サイト内のどこにあるページなのか階層構造を重視したいならページパス
まずは自分のサイトでどのようにURLが構成されているかを把握し、Google Analyticsや他の解析ツールのレポートを見比べてみましょう。
- どのドメイン、サブドメインでサイトが運営されているか
- クエリパラメータはどのくらい設定されているか
- 分析の際にどこまで細かく区別したいか
これらを踏まえて設定をカスタマイズすれば、データがより分かりやすく整理され、分析の精度が高まります。さらにそのデータを基にコンテンツ強化やキャンペーン施策の改善を行えば、成果アップにもつながるでしょう。
ページロケーションやページパスの理解は、精度の高いアクセス解析の第一歩です。
しかし、「設定が合っているかわからない」「GA4でうまく分析できていない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
パキシーノ株式会社では、SEO戦略設計までをサポートしています。
データの見方を整えることで、検索順位だけでなく「成果につながる改善施策」を明確にできます。
次のアクション:
- Google AnalyticsやSearch Consoleなど、主要ツールのレポートで「page_location」「page_path」を実際にチェックしてみる
- 自サイトのURL構造を洗い出し、必要ならば階層の整理やパラメータの見直しを行う
- 社内またはチーム内で、ページロケーションとページパスの定義を共有して、分析ルールを統一する
もし解析やサイト設計でお困りのことがあれば、当サイト内にも関連記事を多数用意しています。ぜひ参考にしてみてください。

FAQ
- ページロケーションとURLは同じ意味ですか?
-
一般的にURLと呼ばれるものに近い概念です。ページロケーションはプロトコルやドメイン、パス、クエリパラメータまで含めた完全なアドレスを指します。
- ページパスは必ず「/」から始める必要がありますか?
-
はい、多くの場合「/」から始まるのが標準的です。たとえば「/blog/entry」などの形で階層を示します。
- ページパスだけで分析するデメリットは何ですか?
-
ドメインやプロトコルの違いを判別しにくく、クエリパラメータ情報がないため、詳細な追跡が難しい点です。サブドメインを複数運営している場合やパラメータを多用している場合は注意が必要です。
- 解析ツールでのレポート項目名が違うのはなぜ?
-
Google AnalyticsのユニバーサルアナリティクスとGA4で名称が変わったり、他の解析ツールが独自に名称を付けていたりするためです。定義自体は似ていますが、ツールごとに表示やパラメータ名が異なることがあります。
- ページロケーションやページパスを変更するとSEOに影響しますか?
-
URLの変更が伴う場合はリダイレクトなどの適切な対応をしないとSEOに影響があります。ページロケーションの変更はそのままURLの変更につながるので、SEOへの配慮が必要です。