顧客満足度(CS)を向上させる方法は?|企業の事例や具体的な顧客満足度を向上させる施策を紹介!

はじめに
企業が持続的に成長し、発展していくためには、顧客満足度(CS)を高めることが欠かせません。顧客満足度とは、顧客が製品やサービスに対して抱く満足の度合いを表す指標です。
顧客満足度が高い企業は、お客様から信頼や好感を得る一方で、顧客満足度が低い企業は、顧客離れや悪い評判の広がりなどのリスクにさらされます。
そのため、顧客満足度を向上させることは、企業経営において最も重要な課題の一つです。
しかし、具体的にお客様の満足度を高めるにはどのような行動をとればよいのでしょうか。
そこで、本記事では、顧客満足度を高めるための取り組みを、企業の事例を交えながら解説していきます。
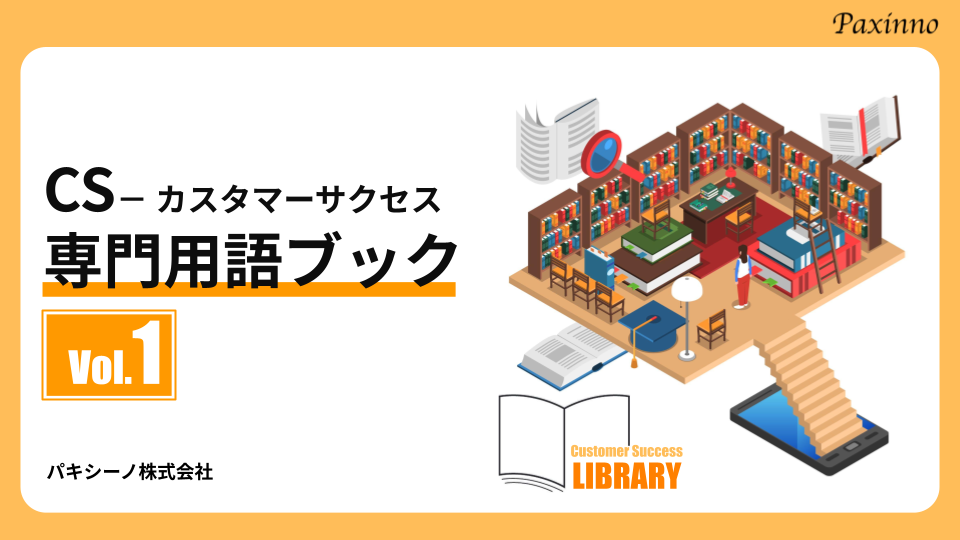
顧客満足度(CS)とは?
顧客満足度(CS)とは、製品やサービスに対する顧客の満足の度合いを表す指標です。企業とのやり取りや交流を通じて得た経験が、お客様自身の期待にどの程度合っているかを示しています。「CS」は「Customer Satisfaction」の略で、「顧客満足」を意味します。
顧客満足度が高いということは、企業が顧客のニーズや期待をしっかりと理解し、期待に沿った製品やサービスを提供できていることを意味します。
お客様からの満足度が高い企業は、お客様から信頼や好感を得て、長期的な関係を築くことができます。
一方、顧客満足度が低い場合、お客様は企業に対して不満を抱えている状態です。そのため、他社に乗り換えようと考えたり、悪い評判を広めたりする可能性があります。これは、企業の評判や業績に大きな影響を与えかねません。
このように、顧客満足度は企業の成長と発展に直結する重要な指標です。顧客満足度を高めることで、リピート購入や口コミによる新規の顧客の獲得、ブランドへのロイヤルティの強化など、さまざまなメリットを得ることができます。
顧客満足度を向上させるための取り組みは、企業の長期的な成功に欠かせない要素なのです。
ここからは、顧客満足度を上げるためにはどうすればいいのか、具体的な取り組みを事例と共に紹介していきます。
顧客満足度を上げる具体的な取り組み
顧客のニーズを理解する
顧客からのフィードバックを集めて分析する
顧客のニーズを理解するには、顧客からのフィードバックを集めて分析することが欠かせません。アンケート調査やインタビューを通じて、顧客の声や要望を把握しましょう。
アンケート調査は、顧客の満足度や製品・サービスに対する評価を数値化することができ、全体的な傾向をつかむのに役立ちます。一方でインタビューは、顧客の生の声を直接聞くことができ、より深い洞察を得ることができます。
例えば、産業用ロボットメーカーのファナックは、顧客からのフィードバックを積極的に収集し、製品開発に活用しています。
ファナックアメリカ、ファナックヨーロッパなどの海外関係会社では、定期的に顧客満足度調査を実施し、製品の性能や使いやすさ、アフターサービスなどに対する評価を数値化しているのです。
また、営業担当者が日々の活動の中で得た顧客の意見や要望を社内で共有し、製品開発部門にフィードバックしています。こうして収集したフィードバックを分析し、次世代の産業用ロボットの開発に生かすことで、顧客の期待に応える製品を提供し続けています。
こうして収集したフィードバックを分析し、次世代の産業用ロボットの開発に生かすことで、顧客の期待に応える製品を提供し続けているのです。
実際に、国内で2022年に実施した顧客満足度調査では5点満点で平均4.31点の評価であり、ファナックは、これらの取り組みを通じて顧客のニーズを把握し、より良いサービスを提供していることが分かります。
ファナックの事例からも分かるように、顧客からのフィードバックを定期的に集めて分析することで、製品やサービスの改善点を明らかにし、顧客の期待に応えることができます。収集したフィードバックは、社内で共有し、各部門が連携して改善策を検討・実施することが大切です。
参照:ファナック株式会社 (FANUC CORPORATION)
ペルソナを作成して活用する
ペルソナとは、顧客の典型的な属性や行動パターンを示した架空の人物像のことです。ペルソナを作成することで、顧客の特性を理解し、ニーズに合わせたアプローチが可能になります。
ペルソナを作成する際は、顧客の属性(年齢、性別、職業など)、行動パターン(購買頻度、利用シーンなど)、ニーズや課題、価値観などを詳細に設定します。
コカ・コーラ社は、ペルソナを活用したマーケティング戦略により、顧客満足度を高めています。主要なターゲット顧客層ごとにペルソナを作成し、それぞれのペルソナに合わせたマーケティング施策を展開しているのです。
また、ペルソナを活用することで、新商品の開発や販促企画の立案など様々な場面で、顧客視点に立った意思決定が可能になります。
例えば、健康志向のペルソナに対しては、「コカ・コーラ ゼロシュガー」といった低カロリーや機能性を訴求した商品を提案しています。「コカ・コーラ ゼロシュガー」は、糖類ゼロでありながら、コカ・コーラ本来の味わいを楽しめる商品として、健康意識の高い顧客に人気があります。
「コカ・コーラ エナジー」は、忙しい現代人のペルソナを想定し、仕事や勉強、スポーツなどのシーンでエネルギーを必要とする顧客のニーズに応える商品として開発されました。
一方、若者のペルソナに対しては、「コカ・コーラ」ブランドを活用したSNSキャンペーンを実施しています。例えば、「#コーククリエイト」キャンペーンでは、ユーザーが自分だけのオリジナルデザインの「コカ・コーラ」ボトルを作成し、SNSで共有することで、ブランドとの親和性を高めています。
参照:コカ・コーラ カスタマー マーケティング株式会社 (cccmc.jp)
このように、ペルソナを活用することで、ターゲットとする顧客に対して効果的なコミュニケーションやマーケティング施策を展開することができます。
また、ペルソナを活用し、新商品の開発や販促企画の立案など様々な場面で、顧客視点に立った意思決定が可能になるでしょう。
従業員満足度(ES)を上げる
従業員教育やモチベーション管理を行う
従業員教育やモチベーション管理は、顧客満足度を高めるために非常に重要な取り組みです。なぜなら、従業員の能力とやる気が顧客サービスの質を大きく左右するからです。
実際に、アメリカでコンサルティングや世論調査を行っているギャラップ社の調査によると、従業員エンゲージメントが高い企業は、顧客満足度が10%高く、収益性も21%高いという結果が示されています。
従業員の能力向上とモチベーション管理のためには、定期的な研修・教育、ロールプレイングの活用、報酬制度の導入、従業員満足度(ES)の向上などの取り組みが効果的です。
ITコンサルティング会社の株式会社NTTデータは、従業員満足度(ES)を重視し、高品質なサービスを提供しています。同社では、「社員第一主義」という考え方を掲げ、従業員の満足度を高めることが、顧客満足度の向上につながると考えています。
NTTデータは従業員の育成に力を入れており、技術研修や資格取得支援など、スキルアップのための教育プログラムを充実させています。2021年度は、従業員一人当たりの平均研修時間が40時間以上に達し、前年度比で20%増加しました。
また、プロジェクトマネージャーなどの重要な役割を担う従業員には、専門的なトレーニングを提供し、リーダーシップ能力の向上を図っています。その結果、顧客満足度調査では、プロジェクトマネジメントに関する項目で95%の高評価を得ています。
さらに、NTTデータは従業員の働きやすい環境づくりにも注力しています。フレックスタイム制度やテレワーク制度を導入し、ワークライフバランスを推進しているほか、社内の福利厚生施設の充実や、従業員の健康管理サポートなども行っています。
その結果、同社の従業員満足度は90%以上と、業界トップクラスの水準を維持しています。
加えて、同社では優れた顧客対応を行った従業員を表彰する制度を設けており、従業員のモチベーション向上につなげています。2021年度は、顧客満足度の向上に貢献した従業員を対象に、のべ200人以上が表彰されました。
このような取り組みを通じて、NTTデータは従業員満足度を高め、質の高いサービスを提供することで、顧客満足度の向上を実現しているのです。
参照:エンゲージメント | NTTデータグループ - NTT DATA GROUP
このように、顧客サービスの質を上げるには、従業員教育とモチベーション管理が欠かせません。これらの取り組みを通じて、顧客満足度を高め、企業の競争力を強化することができるのです。
NTTデータの事例が示すように、従業員満足度を高めることが、顧客満足度の向上と企業の成長につながることが明らかです。従業員の能力開発とモチベーション管理に積極的に取り組み、顧客満足度の向上を目指していきましょう。
顧客ロイヤルティプログラムを導入する
顧客コミュニティの形成
顧客満足度を上げるためには、顧客ロイヤルティプログラムの一環として、顧客コミュニティを形成することも効果的です。なぜなら、顧客同士のつながりを促進し、ブランドへの愛着を深められるからです。
ITソリューション企業の日本オラクルは、「日本OATUG」という顧客コミュニティを運営しています。このコミュニティでは、オラクル製品を利用する企業の担当者が集まり、情報交換や勉強会を行っているのです。
日本OATUGは1998年に発足し、現在では会員数が419社、1,352名に達しています。製造、流通、金融など各業界の主要企業がメンバーとして名を連ねており、オラクル製品に関する豊富な知識を持つパートナー企業も参加しています。
具体的には、日本OATUGでは、定期的にセミナーやイベントを開催し、メンバー同士の交流を促進しており、製品別の情報交換や事例共有の場を提供しているのです。
そして、オラクル社は、このコミュニティを通じて顧客との関係を強化し、製品改善のためのフィードバックを得ています。コミュニティメンバーから寄せられる要望や意見を製品開発に活かすことで、ユーザーのニーズに合った製品を提供できるようになるのです。
また、コミュニティメンバー同士の交流が生まれることで、顧客同士が助け合ったり、共同プロジェクトを立ち上げたりすることもあります。
このような顧客コミュニティは、顧客満足度を上げるための重要な要素になります。顧客同士の交流を通じて、ブランドへの愛着が深まり、長期的な関係が築かれるのです。
実際に、日本オラクルの顧客満足度は高く、同社の製品やサービスに対する評価は業界でもトップクラスです。顧客コミュニティの形成が、こうした高い顧客満足度の実現に貢献していると言えるでしょう。
参照:日本OATUGについて:日本OATUG - オラクルアプリケーションユーザー会 (oatugj.gr.jp)
まとめ
顧客満足度(CS)を高めることは、企業の持続的な成長と発展に欠かせない取り組みです。本記事では、顧客満足度を向上させるための具体的な取り組みを紹介しました。
顧客満足度を高め、顧客との強い信頼関係を築くことで、企業は長期的な成功を手にすることができます。
顧客満足度向上への取り組みを、経営の最重要課題の一つとして位置づけ、全社一丸となって推進していきましょう。
パキシーノ株式会社では、顧客体験に関するコンサルティングを行っています。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。
無料でご相談いただけます。
