【事例】株式会社Fulmo様インタビュー|弊社コンサルティングサービスを受けて
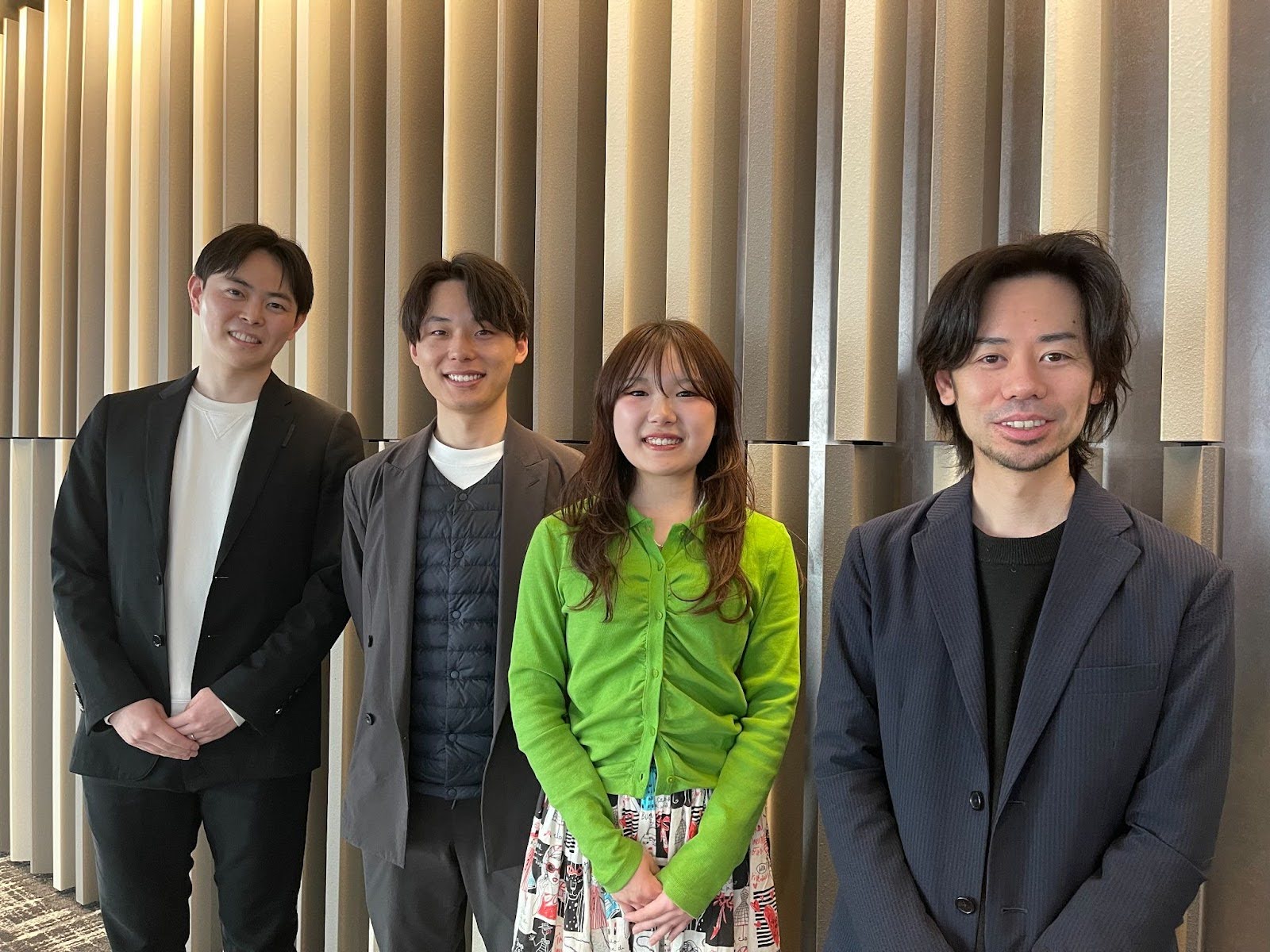
左から、弊社コンサルタント深見、Fulumo株式会社CX担当者 武藤様、CS担当者 香月様、弊社代表 増田。
2024年8月頃、株式会社Fulmo様(以下敬称略)からご依頼を受け、弊社にてカスタマーサクセスの伴走支援事業を開始させていただきました。
「CX(カスタマーサクセス・顧客向けサポート)・CS(問い合わせサポート)を更に強化したい」とご相談をいただき、9月頃より実際の支援を開始させていただいております。
今回は、パキシーノ株式会社代表の増田、弊社のカスタマーサクセスコンサルタントの深見がインタビュアーとして、株式会社Fulmo様にてCXを担当されている武藤様、CSを担当されている香月様にインタビューを実施しました。
株式会社Fulmo様の事業内容について

Fulumo様ホームページ:https://fulmo.co.jp/
増田氏:Fulmo様は具体的にどのような事業をされていたのでしょうか?
武藤氏:2024年6月までは、主に自社で保有するECサイトを運営しており、特定のカテゴリーに特化したECサイトとして展開しておりました。その後、2024年6月ごろから、事業展開を視野に入れ、特定のカテゴリーに特化した「Shoppal」というECサービスプラットフォームの展開に至りました。
増田氏:ペアルックやロリータ系ファッションなど、ニッチな領域において、マーケティングやウェブ集客を行い、自社でECサイトを運営されていたのですね。
武藤氏:そうですね。ペアルックとロリータ服などニッチ領域の運営を開始し、徐々に定型ECとして、月額費用を頂戴し、運営支援を実施するようになりました。はじめは一つ一つのECサイトを個別のサーバーで立ち上げておりました。しかし、その後、事業展開の過程で、単一のサーバー上でECサービスプラットフォームを立ち上げ、SaaSモデルへと移行いたしました。
ECサービスプラットフォームの構想自体は2023年11月頃から始まり、エンジニアがプラットフォームを開発し、2024年6月頃にリリースしました。
増田氏:徐々に「Shoppal」をSaaSとして機能させることになったということですが、それまで武藤様や香月様は具体的にどのような業務を担当されていたのでしょうか。
武藤氏:私自身は、2023年6月頃に自社のサイト運営に携わっていました。その後、2023年7月頃にCX担当としてShoppalのほうに参画することになりました。当時は、組織体制が未整備な状態でしたが、その状態からCX(顧客向けのサポート)部門の最初のメンバーとして、顧客対応を開始いたしました。
始めは、「立ち上げフローのマニュアルが存在しない」という状態から業務を開始したため、徐々にマニュアルを作成しながら、お客様への対応を進めていきました。そのため、分析業務も並行しており、お客様に知識を習得していただきつつ、自身も知識を深めていく形で運営しておりました。
香月氏:私は2023年春頃から参画しています。当時は2名体制でした。CS(問い合わせサポート)部門の現場を継続的に見ており、自社ECの段階からSaaS導入後のフェーズも経験しています。CS部門は、お客様と直接対応するだけでなく、ECの受発注業務を含む全てのオペレーションを最終段階まで担当しております。
増田氏:先ほど、当初はECサイトを個別のサーバーで運用されていたものが、SaaSモデルへ移行されたとのことでしたが、どうしてですか?
武藤氏:元々は、商品追加・商品説明作成・クリエイティブ制作など、全ての業務を代行しておりました。しかし、「これらの業務は誰でも実行可能なのではないか」という考えに至り、集客とシステム開発に特化するためにSaaSモデルへ移行しました。
そして、その他の業務はお客様に委託する運営形態へと変更しています。
増田氏:「誰でも実行可能な業務は仕組み化し、それ以外の部分をお客様に注力していただくことで成功に繋がる」という考えに至ったのですね。
パキシーノ株式会社に支援をご依頼された経緯

深見氏:パキシーノ株式会社に支援をご依頼された経緯についてお伺いしたいです。ECサービスプラットフォーム事業を開始された際のCS部門における課題について、詳しくお聞かせいただけますでしょうか?
武藤氏:当時、メンバーは3名から4名程度の体制でしたが、営業目標から逆算すると、組織の急成長と人員増加が見込まれていました。そのため、CX部門において、既存業務の仕組み化や、お客様がより主体的に業務を遂行できる体制構築が喫緊の課題でした。
また、本来お客様に行っていただきたい業務が適切に遂行されていないという課題もあり、クライアント数の増加に伴い、同等の品質で対応できるかという点も懸念しておりました。
深見氏: 改善を進めるにあたり、CX部門としては具体的な改善策のイメージをお持ちだったのでしょうか。それとも、相談が必要な状況だったのでしょうか。
武藤氏: 具体的なイメージはほとんどなく、「どうすれば良いのかわからない」という状態でした。お客様に行っていただきたいことは明確でしたが、組織拡大に合わせてどのように調整していくかという点については、大きな課題でした。そのため、CSに精通した専門家にご相談したいと考え、増田様をご紹介していただいたという経緯です。
深見氏:ちなみに、当時の武藤様の心情としては、どのような状態でしたか。
武藤氏:まさに「大変だ」という状況でした。相談できる人がおらず、どうすれば良いか途方に暮れていました。誰に聞けば解決できるのか、社内に相談できる人はいないのかと、切実に感じておりました。
深見氏:武藤様が懸命に取り組まれているものの、専門知識が不足しているため、それを補い、事業を加速させるべきだという議論があったということですね。実際、事業は急速に成長していましたよね。
武藤氏: コストをかけてでも顧客獲得を強化しようという方針で、2ヶ月で約十社のクライアントを獲得しました。このペースで成長を続けていけば、一人で50社以上を見ることは不可能だと感じていました。
深見氏:当初は、非常に急速な成長を遂げていましたよね。短期間で多数のクライアントを獲得されていました。
増田氏:仕組みや自動化もまだ整備されていない状況でしたよね。
武藤氏:自動化も全く進んでいませんでした。
香月氏: 私たちも、様々な要因が重なり、リーダーを務めていた者が6月に退職し、私がその役割を引き継ぐことになりました。ちょうどその時、東京で開催された社内MTG会合で、退職の引継ぎと、SaaS事業の急成長に伴う業務の話があり、正直戸惑いました。
引継ぎが十分にできていない状況で、多くの依頼が舞い込み、SaaS側の知識もないまま注文数が増加することへの不安がありました。二人体制で業務を行っていたため、業務が属人的になり、マニュアルも整備されていませんでした。これらの課題を解決するために、外部の専門家にご相談させていただき、分析から支援していただきました。
増田氏: ご相談いただいた当初は、CS部門のオペレーションを改善したいというご要望でしたね。しかし、その際に現状をお伺いしたところ、CX部門も共に大変な状況ではないかという話になり、CSとCXの両部門を支援させていただくことになりました。
実際に、CX部門は多くの課題を抱えており、課題の優先順位をつけていただきながら、オンボーディング設計や満足度調査などの支援を開始しました。
武藤氏: 課題を洗い出す際は、ブレインストーミングのように様々な意見を出し合いましたね。「目標設定をどのように行えば良いのか」という議論や「メンバーをどのように育成すれば良いか」という課題もありました。
深見氏:始めは、顧客満足度を向上させるため、最初の月にアンケートを実施することを目標としていました。しかし、アンケート項目や実施方法について検討し、具体化を進めていく中で、オンボーディング全体の自動化について議論するようになりました。
そこで、オンボーディングフローを可視化し、自動化できる部分を特定していくことで、自動化へと大きく舵を切りましたね。9月、10月は現状把握や課題整理に注力し、10月から12月にかけて自動化を推進していきました。当時は、数百社もの立ち上げプロジェクトが進行中でしたね。
増田氏:はい。 自動化を進めなければ、人員管理やコスト対策が間に合わないという状況でした。当時、オンボーディングにかかる時間を5時間以内に短縮するという目標を設定しましたが、実際にはどのくらいかかっていたのでしょうか。
武藤氏:やりやすい業務かどうかにもよりますが、5時間から6時間程度かかっていたと思います。
深見氏:CX部門は、ポータルサイトと外注の組み合わせで業務を行っていましたもんね。
武藤氏:はい、外注費も相当かかっていました。
増田氏:今後クライアント数を増やしていく上で、コスト削減が必須でした。まずは、一緒にCS、CX両部門の課題を洗い出し、優先順位をつけていきました。そして、自動化を進めることで、コスト削減と業務効率化を実現しました。具体的には、GASやDify、レコメンド機能なども活用しました。
武藤氏: これらの機能は現在も、基盤として利用しております。
増田氏:当初は、CX部門の担当者が手動でキーワードを選定し、キーワードプランナーからデータを取得していました。CS部門についてはいかがでしょうか?
香月氏:CS部門は、一緒に業務全体の可視化から始めました。各業務にかかる時間や課題を整理し、発注業務と問い合わせ対応業務における改善点を探していきました。データが可視化されていない状態からのスタートでしたので、増田さん・深見さんにリードしていただき、決済システムや問い合わせツールの選定、スケジューリング、分析までご支援いただきました。
増田氏:通常業務と並行して可視化や整理を行うのは大変な作業ですよね。
武藤氏:目の前の業務で手一杯でした。顧客対応に追われると、企画を考える余裕がなくなりますよね。
香月氏:その通りですね。特に、引継ぎとCX部門の立ち上げが重なり、業務フローのキャッチアップに時間がかかりました。Slackでの社内連絡に追われる日々でした。
武藤氏:問い合わせ窓口が一本化されるようになって、よかったですね。
パキシーノ株式会社が伴走支援を通して提供した価値

深見氏:多岐にわたる支援をさせていただきましたが、最も役立ったと感じた点はどこでしょうか。
武藤氏:専門家が近くにいるという安心感は大きかったです。解約案件など、すぐに相談できる人がいるのは心強かったです。
香月氏:私も同感です。また、チャネルトークの導入をご支援いただき、マニュアル作成もしていただきました。実装までサポートしていただけたので助かりました。
増田氏:新しいツールは、何を選べば良いか分からないことが多いですよね。
香月氏:長年同じ業務を行っていると、自分たちの業務フローやシステムを客観的に見ることが難しくなります。相談することで、新たな視点を得ることができました。
武藤氏:ミーティングの場で資料作成までしていただけたのは、本当に助かりました。
香月氏:実務的なスキルも学ぶ良い機会になりました。
増田氏:会議中に資料を作成することで、認識のズレを防ぎ、効率的に進めることができます。
武藤氏:個人的には、深見さんがCX部門のロールモデルになってくれたことも嬉しかったです。
深見氏:ありがとうございます(笑)ご提供したアウトプットの中で、武藤様にとって最も良かった点はどこでしょうか。やはり自動化でしょうか。
武藤氏:はい、自動化のスケジューリングやタスク整理、依存関係の整理などは非常に助かりました。プロジェクト管理もスムーズに進みました。そのような整理やスケジュール管理は、一人では絶対にできませんでした。 複数レーンでのプロジェクト進行管理ですね。現在、別のプロジェクトを進めているのですが、まさに同じような形式で進めています。
深見氏: 現在も活用していただいているのですね。
武藤氏: おかげさまで個人的な資産にもなりました。
深見氏: 会社のスケジュール管理にも役立っているということですね。
香月氏: 私も同様です。作成していただいたチャネルトーク推進のスケジュール表は、タスク整理に役立っています。
増田氏: アウトプットベースで一緒に進められたことが大きかったのかもしれませんね。
香月氏: 専門的な知識だけでなく、ベンチャー企業で応用できる仕事のスキルも得られたと感じています。
深見氏: 課題の捉え方によって、得られる価値は大きく変わりますね。
香月氏: これから成長していく段階の企業にとって、非常に価値のある支援だと思います。
深見氏: 今回の話からすると、パキシーノ株式会社のCS伴走支援が、「プロジェクト管理」や「マネジメント」といった、ベンチャー企業が直面しやすい課題の解決に貢献できたということですね。
武藤氏: CX組織の構築というだけではなく、プロジェクト管理やマネジメントなど、課題の整理なども含めて、抽象度の高い支援が大きかったように思います。
伴走支援に感じた課題
増田氏:価値や管理についてお話いただきましたが、今後さらに踏み込んで支援するとしたら、どのような点があるでしょうか。CX、CSそれぞれの視点からお聞かせいただけますでしょうか。
武藤氏:そうですね、一番難しかったのは、ECサイトの成長に関する課題に直面した時、誰に相談すれば良いのか分からなかったことです。
深見氏:オペレーション改善やマネジメントについては相談できても、ECサイトの成長戦略となると、ドメインの専門性が求められますからね。ECサイトの成長戦略とオペレーション改善は別軸で考える必要があり、成長戦略が定まらなければオペレーション改善も進められません。
成長戦略がある程度見えてきた段階で、オペレーション改善に着手する必要があります。
武藤氏: はい、その通りだと思います。
増田氏: 成長を目指す上で、自分たちの専門領域を超える課題に直面したということですね。CS部門はどうでしょうか?
香月氏: 改善プロジェクト全体のスピードをさらに上げられたら良かったと感じています。例えば、週1回のミーティングだけでなく、2〜3回に増やしたり、課題が発生した際にすぐに相談できる体制があれば、よりスムーズに進められたと思います。
これは当社の課題でもありますが、改善意欲を高めることで、より良い結果に繋がったのではないかと考えています。決められた週1回のミーティング以外にも、相談の機会を設けるべきだったと感じています。
増田氏: Slackなどで常に連絡を取り合っていたとしても、リアルタイムでのやり取りは難しいですからね。定例会で状況を把握されていたということですね。
深見氏: ベンチャー企業では、状況が日々変化するため、情報共有の難しさはありますね。方針転換は致し方ない部分もありますが、重要な部分はその都度共有する必要があるということですね。
香月氏: その通りですね。
深見氏: 方針転換は避けられないとしても、全ての情報を常に共有していては時間がかかりすぎるため、どこまで共有するかというバランスが難しいところです。
香月氏: ミーティングは報告が中心になりがちでした。
武藤氏: 情報共有は難しいですね。増田様に社内定例ミーティングに参加していただいたこともありました。部署ごとに定例ミーティングがあれば、そちらにも参加していただくなど、状況に合わせて情報共有の機会を設ける必要があると感じました。オフィスに常駐していただくのが一番良いとは思いますが。
深見氏: そうですね。コミュニケーションも重要です。プロジェクトに関するやり取りだけでなく、社内の状況なども共有できるような関係性を築けると、よりスムーズに進めることができたかもしれません。社内の重要な情報が共有されるチャンネルに、参加させていただくのが良いかもしれません。
増田氏: 情報把握が難しくなりますからね。
深見氏: どこまで情報を共有するか、難しい問題ですね。
今後の展望

増田氏:最後に、今後のCX、CSの組織体制や提供価値についてお聞かせいただけますでしょうか。まずはCX部門についてお願いします。
武藤氏: お客様の売上向上はもちろんですが、現状は、お客様の成長に貢献するには、まだまだできることがあるため、まずは当たり前の基準まで引き上げたいと考えています。その上で、無駄なコストを削減し、一定の品質のサービスを提供していきたいです。
増田氏: その支援を通じて、お客様の成長に貢献していくということですね。
武藤氏: CX部門としては、お客様の成長に貢献できる体制を構築したいと考えています。それが次のミッションです。人的リソースに頼るのではなく、システムで提供できる情報を拡充し、人的対応が必要な部分と、より顧客の成長を促進するためのコミュニケーションに注力したいと考えています。
増田氏:CS部門はいかがでしょうか。
香月氏:CS部門は、SaaS事業の開始に伴い、顧客満足度の指標が購入者様だけでなく、SaaSクライアント様の顧客満足度も重要になってくると考えています。SaaSクライアント様の顧客満足度を長期的に維持するためには、発注から納品、顧客対応に至るまで、高い満足度を確保する必要があります。
そのため、属人化していた業務をマニュアル化、システム化し、守りの体制から、会社の売上に貢献できる体制へと変革していきたいと考えています。優先順位を明確にし、注力すべき点を見極めながら、業務に取り組んでいきたいです。
増田氏: CS部門も、お客様の価値向上を重視するということですね。
深見氏:Shoppalを含め、Fulmo様が今後どのようなお客様に価値を提供したいのか、宣伝も兼ねてお聞かせいただけますでしょうか。
武藤氏:明確に定まっていないですが、1兆円企業を目指しています。上場は当然の目標である考えなので、そこを目指して事業を進めていきたいとも考えています。
増田氏: 上場は素晴らしい目標ですね。その実現にあたり、今後どのようなお客様に利用していただきたいですか?
香月氏: 様々な特定の分野に特化した商品を売るのに、弊社のサービスを利用してくださる方が多くいます。そのため、自分でECを試したいなど自身の事業として展開したいという方に利用していただきたいと考えています。
増田氏: これから事業を始めたい方や、未経験で挑戦したい方にとって、集客は大きなハードルですよね。すでに事業をされている方が、新たな事業として展開するケースも考えられます。ニッチな分野で展開することで、差別化を図ることもできます。
武藤氏: 面白い事業だと評価されることが多いので、リスクを抑えて面白い事業に挑戦したいという方には最適だと思います。BtoCで展開したいというニーズにも応えたいですね。
増田氏: これからのチャレンジも心より応援しております。この度はご依頼頂き、誠にありがとうございました。
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。
無料でご相談いただけます。
